本ブログの御訪問ありがとうございます。
機械設計歴20年以上のtsurfと言います。
今回は以下に関する記事です。
機械設計に使う
近接センサや静電容量センサー
のA接/B接
⇩本記事は以下の方にオススメです⇩

未経験機械設計者
近接センサーや静電容量センサーで
A接とかB接とかって何だよ?
⇩本記事を読むと以下が わかります⇩

今回は静電容量センサーを例に
A接とB接を解説します
①光を使わないセンサー
光電センサーやファイバーセンサーは、
光を使ったセンサーです。
しかし センサーの中には光を使わず
電界の変化や静電容量の変化で検知するセンサーがあります。
例としては、以下です。
- 近接センサー
- 静電容量センサー
これらのセンサーで注意すべき点としては、
購入時にA接/B接を型式で指定しなくてはいけない
ことです。
なぜなら、近接センサーや静電容量センサーは
後から設定で変更できません。
では、『A接/B接とは何か?』
次の章で解説します.
②A接点/B接点とは
A接点 B接点概要
光を使ったセンサーで紹介した
ライトON ダークONに相当するものです
| 検知時 | 非検知時 | ||
|---|---|---|---|
| A接点 | ➡ | 信号ON | 信号OFF |
| B接点 | ➡ | 信号OFF | 信号ON |
参考としてライトON ダークONについては
以下の記事を御参照ください。
A接点とは
以下のように、近接時に被検知物を検知した時に
出力信号をONします。
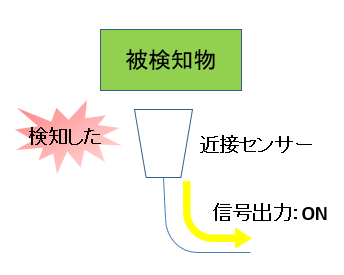
逆に以下のように、被検知物を検知していない時は
出力信号をOFFします。
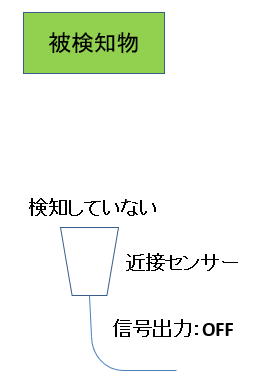
B接点とは
以下のように、被検知物を検知していない時に
出力信号をONします。
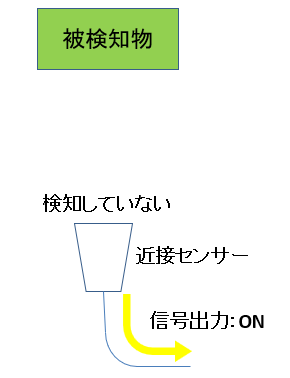
逆に 以下のように、近接時に被検知物を検知した時に
出力信号をOFFします。
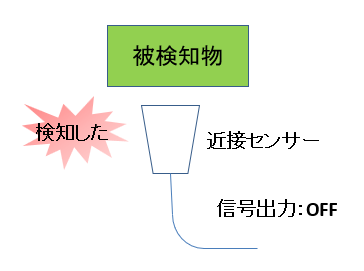
③センサーの出力設定は、断線検知を考慮する
断線検知とは
センサーが断線などで破損した場合に
外部にわかるようにすることです。
特に近接センサーなどでインターロックに
使用する場合は注意が必要です。
詳しくは後述しますが設定法としては、以下となります。
| 使用法 | 使用事例 | ||
|---|---|---|---|
| A接点 | ➡ | ワーク等の確認 | 有ることを確認 |
| B接点 | ➡ | 無いことを確認 | インターロックなど |
<注意>
参考で 詳細や使い分けを後述しますが
会社によって考え方がちがいますので
新規で設置の場合 必ず自社の電気設計担当に確認してください
④A接点を使う場合の例
ワーク有を検知する場合
ワーク検知センサーはワークの有り無しを識別
するものですが、
以下の用途のセンサーの場合
ワーク検知センサーの場合の特徴は
『ワーク等がある』ことを確認します。
あることの確認の時は、
あることが確認できている
近接検出時に信号ONにします。
つまりA接点のものを選定します。
A接点の理由
PLCのほうで、
- 信号ONが正常
- 信号OFFが異常
と設定させると以下となります。
| A接点にして | |
|---|---|
|
|
|
| 近接検出時:信号ON ⇒ワークがある正常時 |
非検出時:信号OFF ⇒ワークがない異常時 |
すると以下の条件で、
信号OFFとなり、装置が非常停止&アラーム発報します。
- ワークがない異常の場合
- センサーの信号線や電源線等が断線した場合
つまり、センサーが破損した状態も
異常と判断され検知することができます。
逆に設定してしまうと・・・
- PLCでは信号ONで異常
- センサーはワーク有りで信号OFF
| B接点にして | |
|---|---|
|
|
|
| 近接検出時:信号OFF ⇒ワークがある正常時 |
非検出時:信号ON ⇒ワークがない異常時 |
上記のようにしてしまうと
以下の状態でも信号OFFなので
- 電源線や信号線が断線した状態
- 電源線や信号線が断線した状態で
かつ、ワークがない状態
ワーク有りと判断されてしまいます。
つまり、断線してしまうと常に信号OFFで正常判断され
- 断線自体もわからない
- ワークがない時でもワーク有りと誤判定される
となってしまいます。
⑤B接点を使う場合の例
搬送ジグ検知センサーの場合
イレギュラーなセンサーですが、クラッシュ回避のため
搬送ジグや搬送アームなどの搬送機構Aが、
安全地帯に回避を確認した後に 別の搬送機構Bが通る場合
搬送機構Aがない時⇒別の搬送機構Bが進むのを許可
搬送ジグ検知センサーの場合の特徴は
『搬送機構Aがない』ことを確認します。
ないことの確認の時は、
あることが確認できている
非検出時に信号ONにします。
つまりB接点のものを選定します。
B接点の理由
PLCのほうで、
- 信号ONが正常
- 信号OFFが異常
と認識させると、以下となります。
| B接点にして | |
|---|---|
|
|
|
| 非検出時:信号ON ⇒搬送機構Aがない正常時 |
近接検出時:信号OFF ⇒搬送機構Aがある異常時 |
すると以下の条件で、
信号OFFとなり、装置が非常停止&アラーム発報します。
- 搬送機構Bを動かすタイミングで
搬送機構Aがある異常の場合
- センサーの信号線や電源線等が断線した場合
つまり、センサーが破損した状態も
異常と判断され検知することができます。
逆に設定してしまうと・・・
- PLCでは信号ONで異常
- センサーは搬送機構A有りで信号ON
| A接点にして | |
|---|---|
|
|
|
| 非検出時:信号OFF ⇒送機構Aがない正常時 |
近接検出時:信号ON ⇒送機構Aがある異常時 |
上記のようにしてしまうと
以下の状態でも信号OFFなので
- 電源線や信号線が断線した状態
- 電源線や信号線が断線した状態で
かつ、搬送機構Bが動作する時に
搬送機構Aがある状態
搬送機構Aが回避したから
搬送機構Bが動作OKと判断されてしまいます。
つまり、断線してしまうと常に信号OFFで正常判断され
- 断線自体もわからない
- 搬送機構Aが回避移動されたと誤判定される
となってしまいます。
⑥まとめ
- 近接センサーや静電容量センサーは、
A接/B設を後から変更できないものが
ほとんど - A接点とは、近接検知時に信号出力ON
断線検知を考慮すると
あることを確認したい場合に選定 - B接点とは、非検出時に信号出力ON
断線検知を考慮すると
ないことを確認したい場合に選定
本記事は以上です。
最後までお読み頂きありがとうございます。