本ブログの御訪問ありがとうございます。
機械設計歴20年以上のT.surfと言います。
今回は以下に関する記事です。
3DCADによる機械設計の基本
トップダウン設計
⇩本記事を読むと以下が わかります⇩
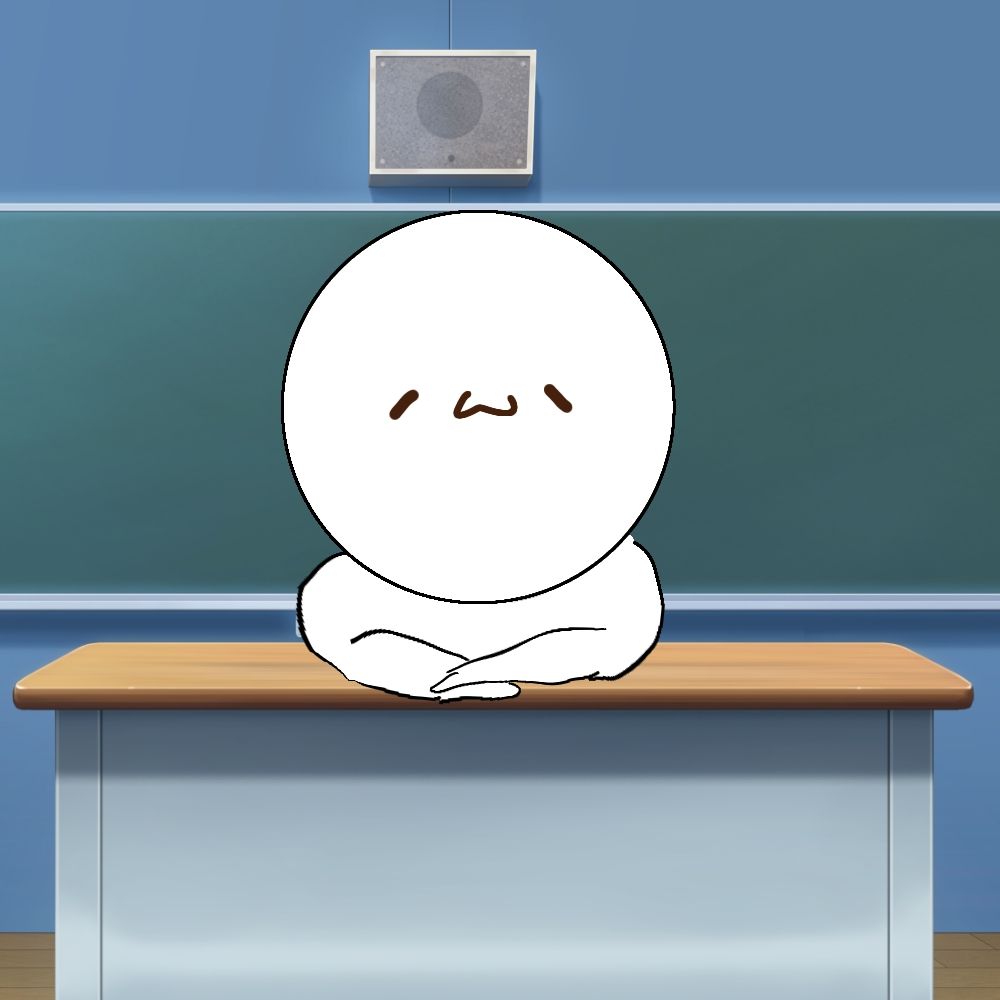
3DCADの基礎知識として
トップダウン設計
について解説します。
本記事は
- これから機械設計を
3DCADで進めようとしていこうとしている方 - 3DCAD導入を検討している企業様
におススメで、
以下の記事の補足解説記事です。
①トップダウン設計の概要
3DCADのトップダウン設計とは
まずは2Dレイアウトで構想設計を行います。
その過程で
- 装置の上面視(各機構の全体配置)
- 様々な断面(機構が成り立つ検討)
がなされます。
そして、その上面視と様々な断面から
詳細設計として3D設計をしていきます。
2D構想設計⇒3D詳細設計
というまさにトップからダウンという
機械設計の効率的な流れを
トップダウン設計と言います。
②トップダウン設計の流れ
2D構想レイアウト
3DCADにおける機械設計の本質は
実は3D空間上で行う2Dレイアウトです。
2Dレイアウトは
- 上面視(機構の配置)
- 複数の断面図(機構の断面検討)
を別々に検討できるという
3Dにない自由度の高い構想検討が可能です。
この2Dの自由度の高さにより実は
構想レイアウトの段階では2Dのほうが
質の高い(自由度の高い)検討が短時間で可能
という特性を持っています。
この各断面の検討があるからこそ
それが成り立つ3Dが発想可能
なのです。
ですので、ある程度2Dレイアウトによる
構想設計が進んだ後
任意のタイミングで詳細設計にはいります。
3D詳細設計
さきほど 構想レイアウトは2Dのほうが
効率がいいと話しました
ですが、その詳細設計の段階では
3Dのほうが立体的検討ができるので
質が高く短時間で可能なのです。
2Dレイアウトで上面視や様々な断面で
全体が検討されています。
その上面視、様々な断面から、
そのレイアウトが成り立つ3D形状が作成できるのです。
逆に言うと2Dレイアウトがあるからこそ
スムーズな3D作成が可能なのです。
要は使い分けの問題です。
- 構想設計は2Dのほうが質の高い構想設計が可能
- 詳細設計は3Dのほうが質の高い詳細設計が可能
という2Dと3Dの各メリットを生かして
全体として質の高い検討を短時間で行うことを
トップダウン設計と言います。

③トップダウン設計の特色
3DCADが優れているのは
この2Dレイアウトをアセンブリファイル内の
3D空間上の平面で行うことができる
ということです。
しかも機構毎に違う平面で断面を作成できます。
そして、構想段階では
- 上面視(機構の配置)
- 複数の断面図(機構の断面検討)
上記を別々に検討できる2Dの特性を活かし
2Dで行うと言いました。
別々に検討された上面視と複数の側面視から
それが成りたつための3D形状が
根拠のある絶対形状として
根拠のある絶対位置に配置
されます。
この特色はICADなどのノンヒストリーCADで可能な
トップダウン設計特有なものです。

別記事で解説する
ソリッドワークスなどのヒストリーCADでは不可能で
ヒストリーCAD特有のボトムアップ設計とは
対をなすものです。
ボトムアップ設計は
根拠のない形状を作成して
根拠のない相対位置に配置
という非論理的な設計方法です。
④トップダウン設計の流れからわかること
2Dと3Dの使い分け
上記の流れからわかる通り2Dと3Dの使い分けですね。
- 設計初期の構想レイアウト
⇒2Dレイアウト - 設計中半からの詳細設計
⇒3Dでの設計
と、上記のように
2Dと3Dの持つそれぞれのメリットを理解して使い分けて
質の高い検討をするわけですね。
従って、一部のヒストリーCADメーカーが
勘違いをしているようですが

CADメーカー
3Dがメインになるから
2Dはいらないね
と言う考えは根本から間違っています。
今までの設計に問題があったとするのであれば
全て2Dでやってきたことが問題であって
2Dそのものが問題なのではないのです。
拘束や履歴は必要ない
そして、トップダウン設計の流れを見て
もう一つ理解できることがあります。
3Dで詳細を詰めることになる部品の以下
- 根拠のある絶対形状
- 根拠のある絶対位置
は2Dレイアウトによって決定している
ということです。
2Dレイアウトの段階で5~6割は決まっていて
3D化の過程でさらに詳細を詰めていくだけです。
従って、
ソリッドワークスなどのヒストリーCADのような
- 寸法拘束で形状が決まるわけではありません。
- 位置拘束で位置が決まるわけではありません。
ヒストリーCADはただでさえトップダウン設計が
やりづらいところに来て
ヒストリーCADの寸法拘束やら位置拘束が
設計の邪魔でしかありません。
⑤まとめ
つまり、3DCADを導入するにあたり、
トップダウン設計を想定すべきです。
いや、言い換えます。
トップダウン設計が、できるかできないか
ではなく、
トップダウン設計が、やりやすいかどうか
を基準で3DCADを選定すべきです。
なぜなら、最近のヒストリー系CADも
トップダウン設計を実装しはじめています。
なので、どんなCADメーカー
例えばヒストリーCADのメーカーに聞いても

メーカー
トップダウン設計?
できますよ。
と言うと思います。
しかし、ここで騙されてはいけません。
ヒストリーCADは、トップダウン設計が非常に
やりづらいのです。
なぜならCADとしての自由度がまったくないからです。
実質的に不可能に近いと思ってもらえばいいです。
自由度のないヒストリーCADでどうやって
2Dレイアウト機能を実装しているかと言うと
別に2Dレイアウト機能を設けています。
ですが、ヒストリーCADメーカーは
トップダウン設計における2Dレイアウトを
よく理解していないためか
設計者が欲しい2Dレイアウト機能ではありません。
なので、ヒストリーCADの自由度のなさから
針の穴を搔い潜る努力をして別の方法で
2Dレイアウトの方法を模索しなくてはいけません。
しかし、それでもCADの自由度のなさから
トップダウン設計が非常にやりづらいです。
以下の記事は管理人が
ヒストリーCADソリッドワークスで以下を解説します。
- ソリッドワークスが実装する
2Dレイアウト機能が使えない理由 - ソリッドワークスで
自由度のないシステムの穴を掻い潜り
発見した2Dレイアウトのやり方
トップダウン設計を断然やりやすいのは
ノンヒストリーCADです。
間違えのないように
本記事は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございます。