本ブログの御訪問ありがとうございます
機械設計歴20年以上のtsurfと言います
今回は以下に関する記事です
【機械設計の物理】力の分解(例題1:斜めに荷重の掛かるブラケットの強度計算)
⇩本記事は機械設計初心者の方で以下の方にオススメです⇩

未経験機械設計者
機械設計に使える基礎的な物理を勉強したい
⇩本記事を読むと以下が わかります⇩

今回はブラケットの
断面検討の例題を交え
力の分解を
わかりやすく説明します
- ①力の分解 解説モデル 斜めに荷重の掛かるブラケット
- ②ブラケットに発生した荷重の分解
- ③ブラケットに掛かる分解された荷重の解説
- ④ブラケットの強度計算や断面検討の手順
- ⑤曲げに対する断面の安全形状設計手順
- ⑥実際の計算
- ⑦結論
①力の分解 解説モデル 斜めに荷重の掛かるブラケット
図1をご参照ください
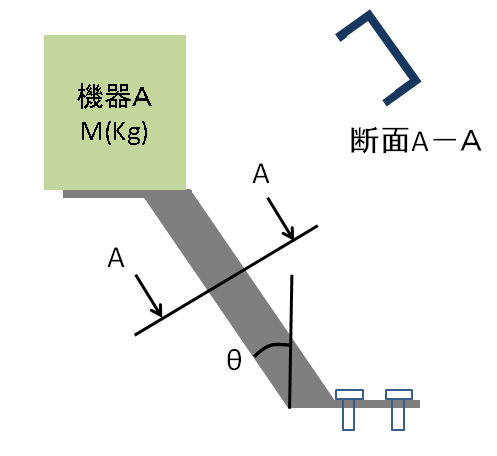
図1 重い荷重を斜めに支えるブラケット
取り付け面から角度Θで 立ち上がっている
ブラケットの先端に荷重M(kg)の機器Aが取り付けられています
この荷重M(kg)が重いのですが
ブラケットはコストダウンのために
立ち上がり部の形状は 断面A-Aで示すような2tの鉄の板を曲げてできる
仮定断面を考えました
機器Aが重量物である以上
仮定断面のブラケットの強度を強度計算によって検証し
場合によっては最適化します
以上の想定のもと 力の分解と 強度計算を解説します
②ブラケットに発生した荷重の分解
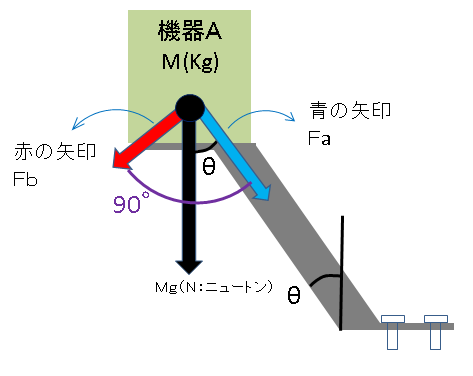
図2 ブラケットに掛かる力を分解
まず 機器Aが重力によって 引っ張られる(加速される)力である
黒い矢印Mg(N ニュートン)が働きます
しかし 図2のように
青い矢印と赤い矢印に荷重が分解され ブラケットに負荷として掛かります
そして 力の分解の際 それを起因させた角度のものが基準になります
例えば 今回の場合ブラケットの立ち上がり角度θが基準となり
その角度で 青い矢印の向きが決まります
赤い矢印は 今回の場合斜面Θに対して90°となります
どうしてそうなるのか③で解説します
③ブラケットに掛かる分解された荷重の解説
では 一つ一つの力について解説します
青い矢印Fa
ブラケットの立ち上がり部に対して
仮定断面(断面A-A)に対して垂直に掛かる成分で
このブラケットの支柱を矢印方向に圧縮させようとする力です
赤い矢印Fb
斜面Θを垂直方向に押して ブラケットの機器A側の端面から 矢印方向に 支柱を曲げて
やろうとする力です
力の大きさの計算式は図3より 以下となります
Fa=Mg・cosθ
Fb=Mg・sinθ
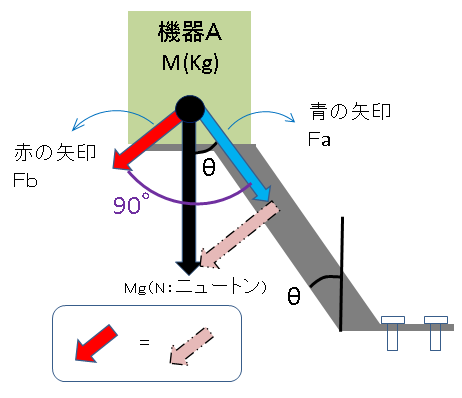
図3 力の成分の計算式
④ブラケットの強度計算や断面検討の手順
概要
上述の通り このブラケットには二種の荷重が
掛かることになりますので強度計算も 以下の2つの検証が必要です
・曲げ荷重に対する強度検証
・圧縮荷重に対する強度検証
手順の流れの説明
手順1 荷重による曲げに対し強度のある断面形状の策定
曲げに対する強度は断面形状に依存します
現状は まだ 仮断面です
強度計算をし 強度が満足できなければ 強度を満足する形状にしていきます
⇩
手順2 圧縮荷重に対する確認
圧縮荷重や 引っ張り荷重に対する強度は断面席に比例します
手順1で作成された断面に対して 圧縮荷重の確認をします
手順の流れの理由
曲げに対する 強度がOKであれば
圧縮荷重に対する強度は割と問題無いことが多ので 上記の手順のほうが
効率がいいことが多いです
もし圧縮強度が不足であれば 断面積を増やしてあげればいいだけです
⑤曲げに対する断面の安全形状設計手順
手順1 仮定断面で どのくらい撓むかを確認します
撓みとは 下図 図5のように どのくらい 曲がってしまうかです
図5でのy(mm)で示している変位量です

図5 撓み
なお どのくらい 撓みを許容できるかどうかは 勘や感覚論と
なってしまいますが 私はだいたい0.3mm程度以内の撓み量としています
注意点として曲げとは 以下の図のように
曲がる外側が引っ張りを受け 内側が圧縮を受けるのですが
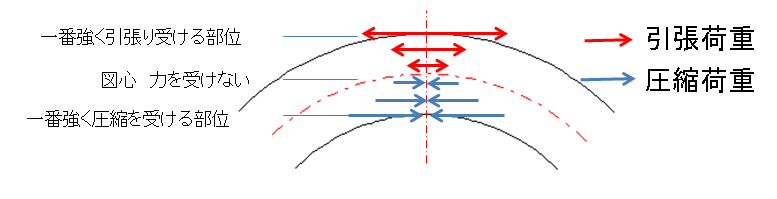
あまり大きい幅を許容してしまうと この’一番引張を受ける部位’
にかかる 引張応力が 実は弾性範囲を超えている場合があり
実際に乗せてみたら ブラケットが破損ということもあるかもしれません
参考記事:【強度計算の基礎】応力 応力歪線図 ヤング率 - tsurfの機械設計研究室
手順2 撓み量が多ければ断面の形状を変更する
こういう時もエクセルで計算をしておいたほうが
寸法部の変更だけで 撓み量の結果を見ることができるので楽です
⑥実際の計算
ここからは 実際に 計算しながら 進めましょう
条件を 以下の図とします
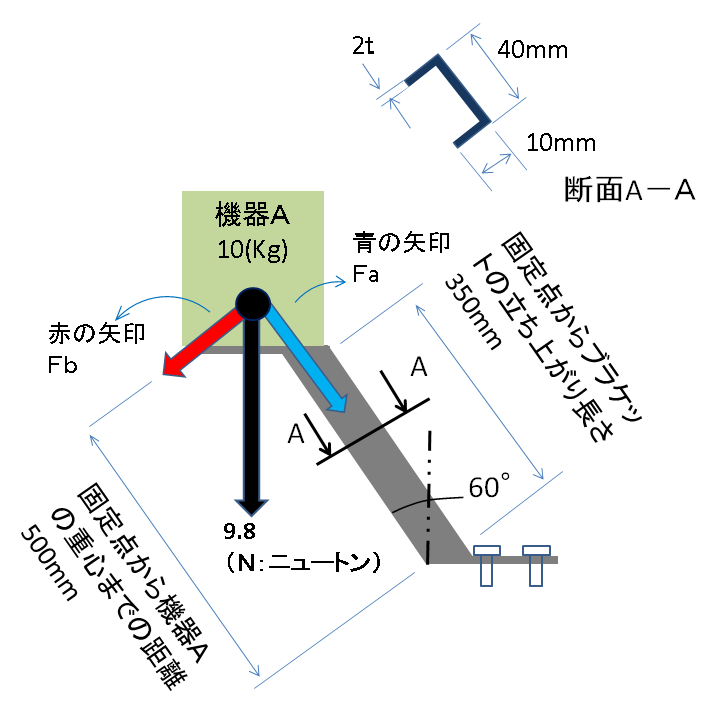
まず 基本的な要素として以下を求めましょう
・ブラケットを圧縮させる力:Fa
・ブラケットを曲げる力:Fb
さらに
・Fbから算出される曲げモーメント:Mb
計算を楽にするためにエクセルを使い 計算をします
(参考記事:選定計算 強度計算 ミスを無くし早くできるエクセル活用術)
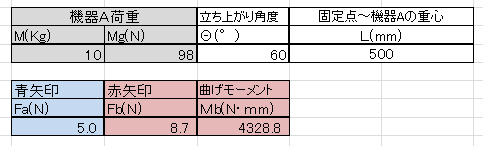
手順1 仮定断面で どのくらい撓むかを確認します
撓みの式です
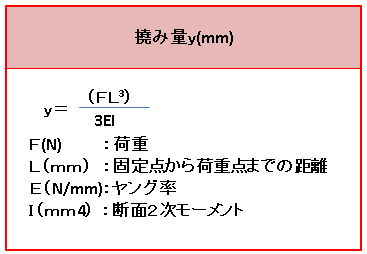
今回の場合
F:Fbである分解荷重
L:固定点から機器Aの重心までの距離 500mm
E:ヤング率は 材質毎に違いネットで調べられます
(参考記事:【強度計算の基礎】応力 応力歪線図 ヤング率)
I:断面2次モーメント
以下を参照
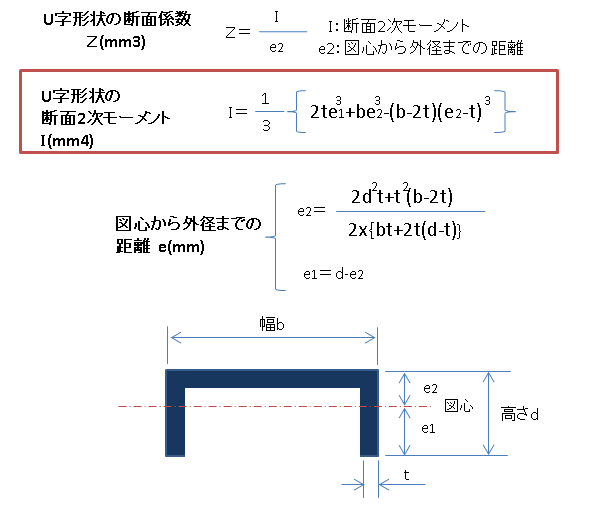
エクセルで計算をします

仮定断面の撓み量は 2.28mmです
大きすぎです 修正が必要です
手順2 撓み量が多ければ断面の形状を変更する
以下の記事でも解説しまたが 高さを変更したほうが有効です
10mmの高さを25mmにしてみましょう
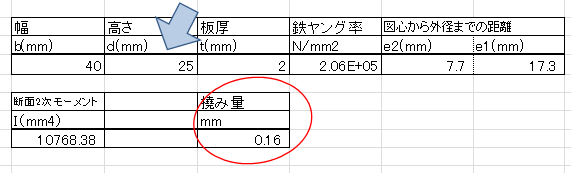
撓み量0.16mmになりました
高さは25mmにしましょう
手順3 圧縮荷重の確認
この検討断面と 圧縮荷重Fbから この断面に掛かる圧縮応力を求めます
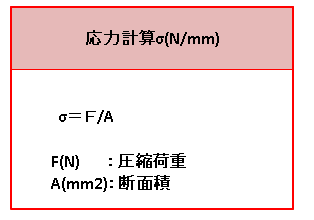
上記より以下となります
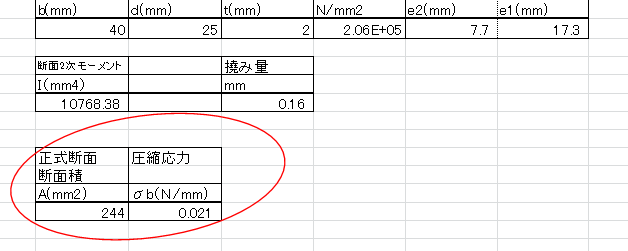
では実際の圧縮量も計算しましょう

今回のLは固定点からブラケットの立ち上がり長さ350mmです

計算するまでもなかったですね
圧縮応力も 応力歪線図での 弾性範囲内です
⑦結論
今回の機器Aを支えるブラケットの断面形状は以下で決定です
曲げ強度 圧縮強度と共に十分な強度です
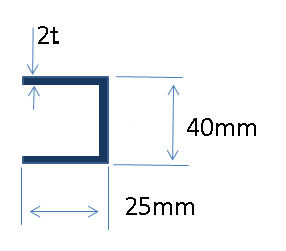
最後までお読み頂きありがとうございます
以上 ご参考まで